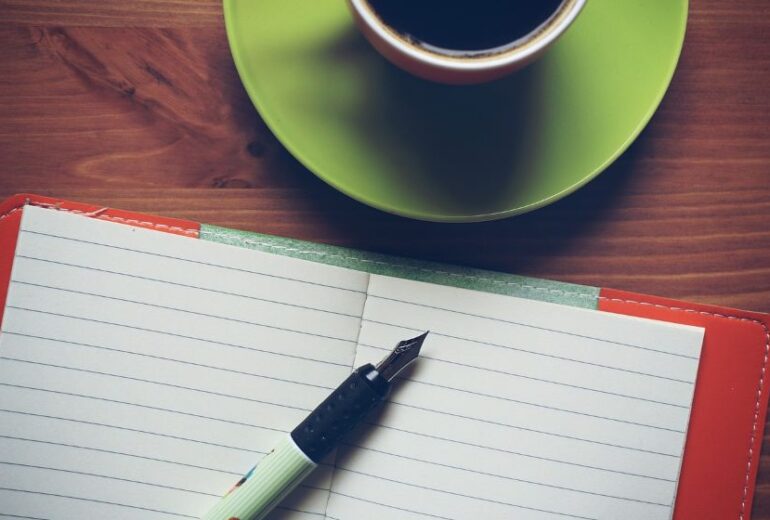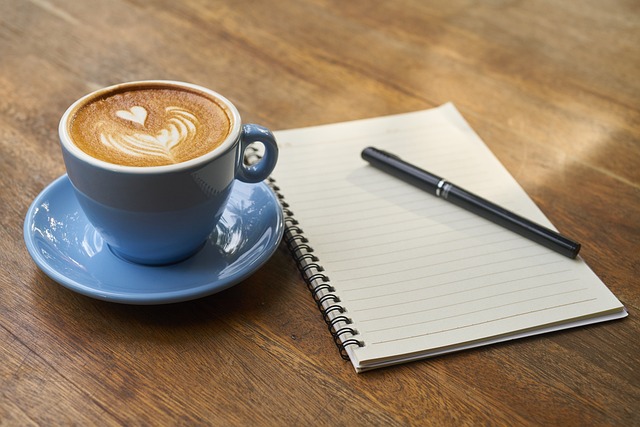10月より、新卒採用のエントリーを開始しています。そこで、今回は学生の皆様に向けて、ご挨拶代わりの記事を書きたいと思います。

UPDATES 最新情報 2025年10月1日 2027年度の新卒採用エントリー受付を開始しました。 2025年4月24日 2026年度の新卒採用エントリー受付は終了しました。 2024年10月9日 新入社員インタビュー記事をブログにアップしました。 CEO MESSAGE ...
最近、「AIに仕事を奪われる」という言葉をよく耳にします。ChatGPTや画像生成AIなど、これまで人がやってきた作業が一瞬でできるようになり、「人間の出番はもうないのでは?」と不安に感じる学生さんもいるかもしれません。
でも、私たちが現場で日々感じているのは、むしろAIが得意なことと、人間が得意なことの棲み分けがはっきりしてきたということです。
AIが得意なこと、人間が得意なこと
AIは、データの分析やパターン認識、正確な繰り返し作業が得意です。たとえばソースコードの最適化やドキュメントの要約などは、AIに任せるとスピードも精度も圧倒的です。
一方でAIが苦手なのは、「目的を定義すること」や「相手の感情を読み取ること」。つまり、“そもそも何を解決すべきか”を考える部分です。
たとえばお客様が「見積書を自動化したい」と言ったとき、本当に困っているのは“自動化”ではなく、“承認フローが複雑で時間がかかること”だったりします。こうした言葉の裏にある本音や課題を察する力は、まだ人間にしかありません。
現場でも感じる「人間らしい仕事」
株式会社エクステックの開発現場でも、AIツールを使う機会は確実に増えています。コードの自動生成、文章の下書き、テストケースの作成など、AIは心強い相棒です。
でも、最終的に「これでいい」と判断するのは人間です。私たちはAIの提案をそのまま受け取るのではなく、“このお客様の現場に本当に合うか?”を考えながら使いこなしています。
つまり、AIに使われるのではなく、AIを使いこなす側でいることが大切。そのためには、観察力・想像力・コミュニケーション力といった“アナログなスキル”が欠かせません。
AIと共に働く時代に求められる力
AIを使いこなす上で大事なのは、「問いを立てる力」です。AIは質問が曖昧だと、曖昧な答えしか返してくれません。逆に、的確な問いを立てれば、AIは人間の何倍ものスピードで答えを導き出します。
この“良い問い”を立てるには、現場感や相手の立場への理解が不可欠。学生時代の課題解決経験やチーム活動での気づきも、実はこのスキルの原点になります。
エンジニアというと「プログラムを書く人」と思われがちですが、実際は「課題を見つけて、仕組みで解決する人」。その過程でAIは心強いパートナーになってくれます。
これから社会に出るみなさんへ
AI時代に求められるのは、「AIより速く」「AIより正確に」ではありません。AIと一緒に、より良い判断をしていける人です。
人と人のつながりを大事にしながら、テクノロジーの力を最大限に活かす。そのバランスを楽しめる人こそ、これからの社会で一番輝くのだと思います。
エクステックでは、そんな“AI時代の人間らしさ”を大切にしながら、日々の開発や業務に取り組んでいます。就職活動を通じて、もし「人の想いと技術の両方に向き合う仕事」に興味を持った方がいれば、ぜひ一度お話ししましょう。